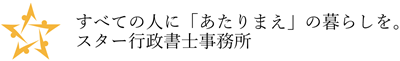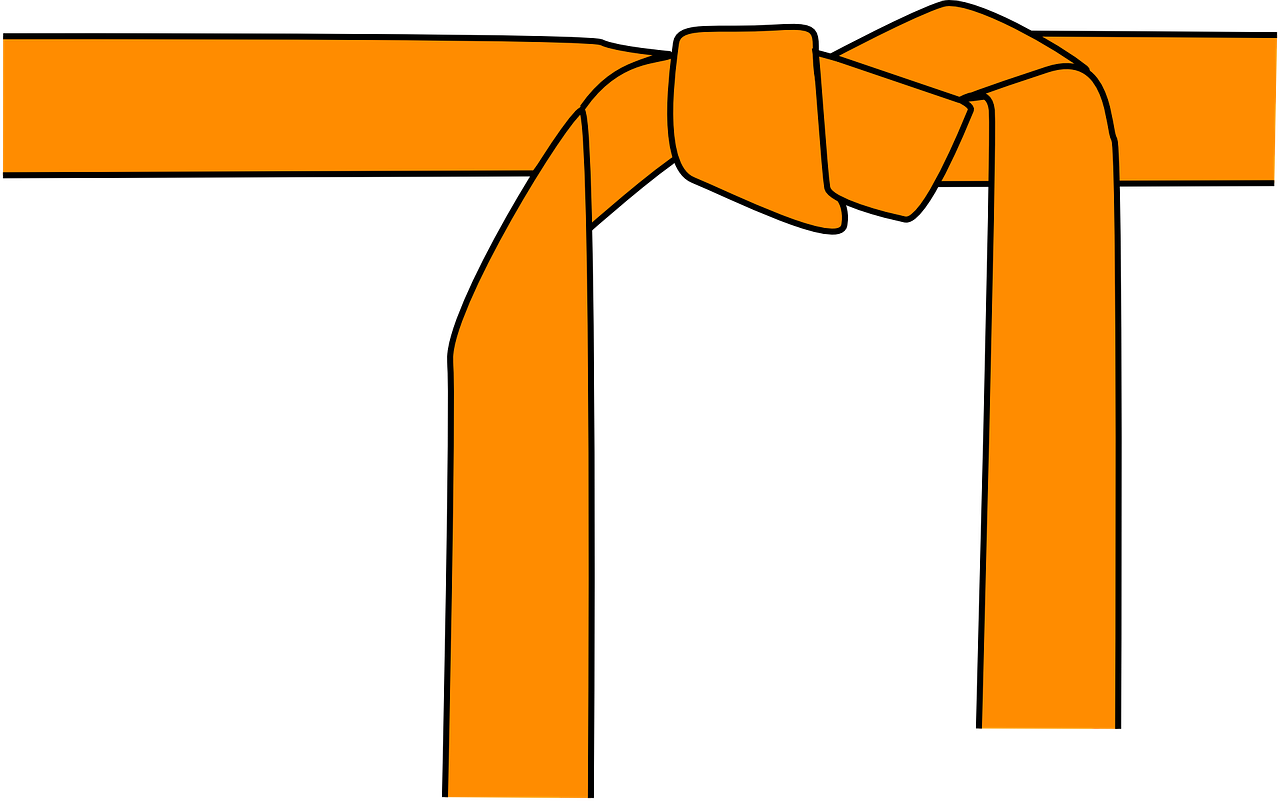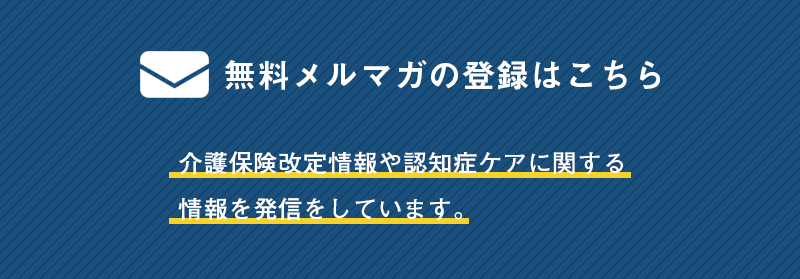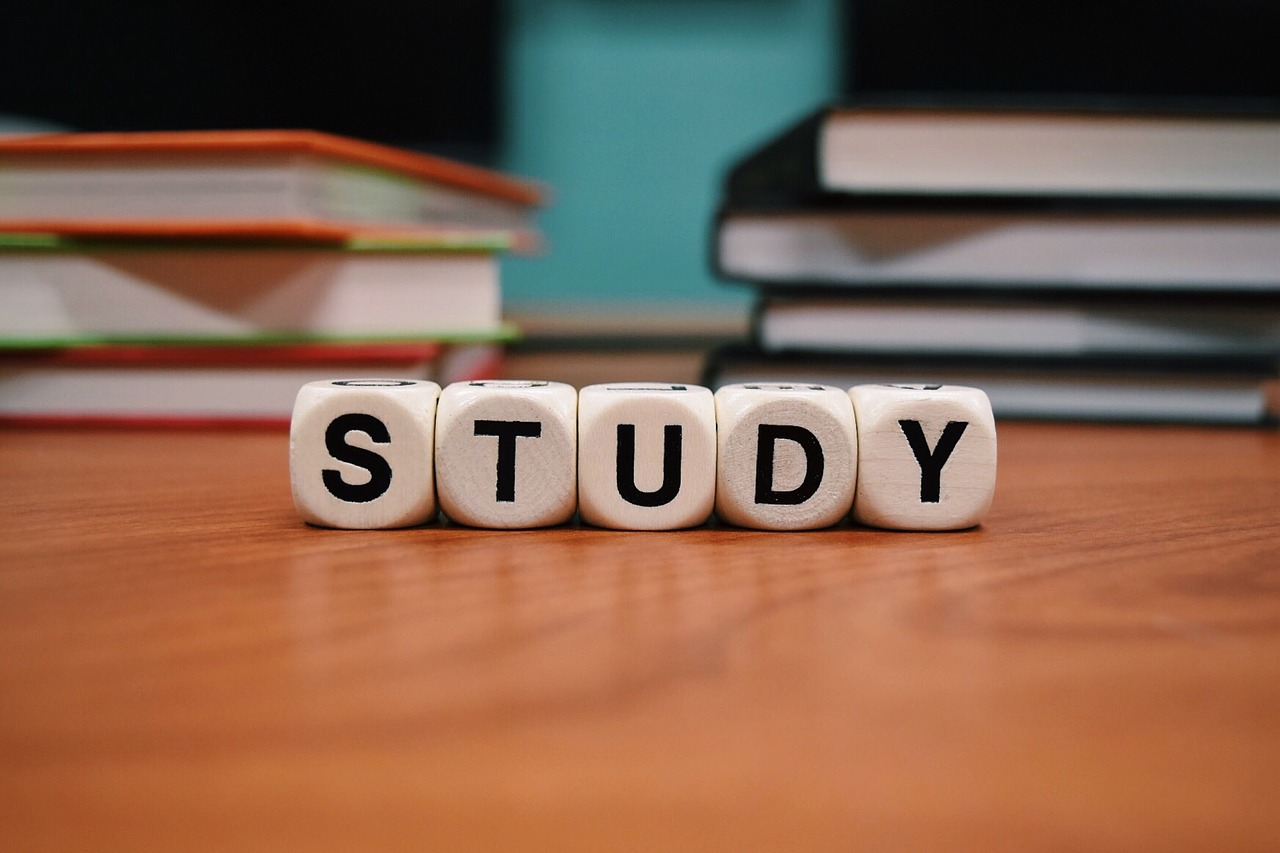介護保険制度では、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合(切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たす場合)を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないとされています。
しかし、高齢者福祉施設では、上記3要件を満たさないにもかかわらず、身体拘束をしている場合があります。
では、なぜ高齢者福祉施設から身体拘束をなくすことはできないのかを考えてみます。
目次
介護保険制度の開始前
冒頭介護保険制度では、緊急やむを得ない場合を除き、利用者の行動を制限する行為は禁止されていると書きました。
では、介護保険が始まる前の高齢者福祉施設はどうだったのでしょうか。
20年前の記憶をたどって書いていきたいと思います。
私が介護の仕事を始めたのは、1999年、介護保険開始の直前です。
その当時は、身体拘束を禁止する明確な基準などなく、その取り組みは各事業所(法人)に委ねられていたと思います。
私が働いていた特別養護老人ホームでは、車いすからの転倒やベッドからの転落を防止するために、車いすの拘束ベルトやベッドに4点柵を使用していました。
当時は、そのような対応方法が当たり前。
もし、ベルトや4点柵を忘れてしまったときは上司から注意を受けるという今では考えられない対応方法でした。
また、オムツの中に手を入れて手が汚れてしまう、汚れた手で色々な所を触ってしまうというご利用者には、つなぎ服、体を掻いてしまう人にはミトン型の手袋をしてもらっていました。
このような介護方法は私が働いていた特別養護老人ホームだけではなく、その当時の高齢者福祉施設では当然のこととして行われていたと思います。
私が、福祉専門学校に通っていた時の実習先の中には、車いすのベルトを使用するだけではなく、車いすを自操する利用者の車いすと手すりをヒモで縛り、ご利用者が自操できないようにしている施設もありました。
介護保険開始直後
そして2000年、介護保険制度が始まります。
制度の開始によって身体拘束は原則禁止になります。
当時は、どこの事業所も混乱していたのではないでしょうか。
なぜなら、これまで身体拘束をすることが正しいと思っていたのに、日付が変わってからは禁止になるのですから。
私は、働いていた施設の仲間と共に身体拘束廃止の研修に参加しました。
その中では、実際に身体拘束廃止に向けて取り組みをしている、病院の施設長や介護現場の人が話をしてくれました。
主な話の内容は、「事業所の身体拘束をなくためにはトップの決断が大切。」「なぜ、ご利用者は車イスから立ち上がろうとするのか。オムツの中に入れてしまうのか、情報収集し、その原因に対応すること。」「身体拘束を外せる人から取り組むこと。」を具体的な方法を交えながら、話してくれたと記憶しています。
その後、事業所内で身体拘束をしている個々のご利用者ごとに情報収取し、その人の身体拘束を外すことによって事故が起きる可能性がどの程度なのか、施設全体で事故防止のために対応方法を検討しました。
その後、徐々に身体拘束を外していくことができました。
現在
私は、行政書士として仕事を始める前は、特別養護老人ホームの生活相談員兼ケアマネージャーとして仕事をしてきました。
その特別養護老人ホームは、定員170名(うち重度認知症対応棟32床)という大規模な施設でした。
そこでは、約10年間、一度も身体拘束はしませんでした。
働いていた特別養護老人ホームの人員配置が、他の事業所と比較して特別厚くなっているわけではありません。
では、なぜ身体拘束をしないでケアできたのか。
私はその理由を次のように考えます。
①要件を満たすことがなかった。
②事故の危険性があることを事前に家族にしっかりと説明していた。
③個々の職員が身体拘束ということを知らなかった。
要件を満たすことがなかった
まず、①から。
170人の介護が必要な方が生活しているわけですから、当然、転倒の危険性や、異食、他者とのトラブルなど様々な事故はありました。
しかし、「切迫性」、「一時性」、「非代替性」という3要件という場面がなかったのだと思います。
特に、3つの要件のうち「非代替性」の要件を満たすことはありませんでした。
施設での取り組みの姿勢として、3つの要件をなるべく狭く考えていく方向でしたので、例えば、ケアワーカーが一人しかいない時間帯に転倒してしまう可能性があるご利用者がいるため、他のご利用者の介助ができない、といった場合でも、代わりに多職種が介護現場に行き、事故の無いように見守る、などといった対応をしていました。
事故の危険性があることを事前に家族にしっかりと説明していた。
②について。
入居申し込み時には必ず入居を希望する人のご家族に施設の見学をしてもらい、そのときに施設の方針と事故の危険性があることを説明していました。
説明の仕方としては、「施設の方針として、ご本人の自由や尊厳をできるだけ守りたいと思っているので、身体拘束は一切していない。しかし、限られた職員数でやっている以上どうしても事故が起きてしまうことがある。そのような危険があるときはご家族にも一緒に考えてもらいたい。」といった話をしていました。
輪の中に家族も入ってもらうイメージです。
しかし、事前に説明をしていても、実際に事故が起きた場合、ご家族から「施設の責任ではないか?」と言われたこともあります。
その場合、事業所として道義的謝罪をし、丁寧に説明しても、ご家族に納得していただけなければ裁判所に訴えられるかもしれません。
もし「ご家族に事故の責任について問い詰められるのが嫌だから、身体拘束をする。」というのはあまりにも本人主体とはかけ離れたケアになるでしょう。
個々の職員が身体拘束ということを知らなかった。
最後に③について。
長い間、身体拘束を行わないと、職員は、以前身体拘束をしていたことを忘れてしまったり、新しい職員は身体拘束自体を知らないまま仕事することになります。
その結果、転倒事故の危険性があるご利用者がいても、身体拘束という対応方法ではなく、それ以外で何ができるか考えるようになります。
当然、すぐに結果が出るとは限りませんが、何度も話し合いや対応方法を繰り返していきます。
最後に
多くの介護施設では、深刻な人材不足に悩まされているところも多いでしょう。
身体拘束をする理由は、
「少ない職員数の中でどのようにご利用者の安全を確保できるか。」
「転倒などの事故が起こった時に、職員が責任を問われるのではないか。」
といったことが挙げられます。
転倒事故が起きた時に、事業所(法人)の法的責任(損害賠償責任)が問われることがあっても、個々の職員が責任を問われることはまずありません。ですので、個々の職員が責任を問われるか否かが問題なのではなく、事業者のトップが身体拘束についてどのように考えているのか否かが問われているのだと思います。
また、ご利用者の身体拘束を通じて、「ケアの本質とは何か」ということを考えていくことが必要かと考えます。