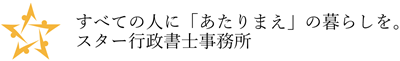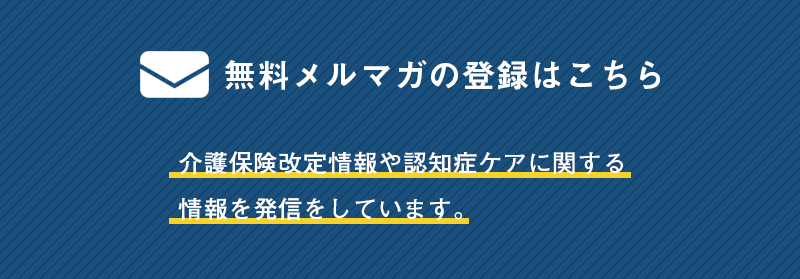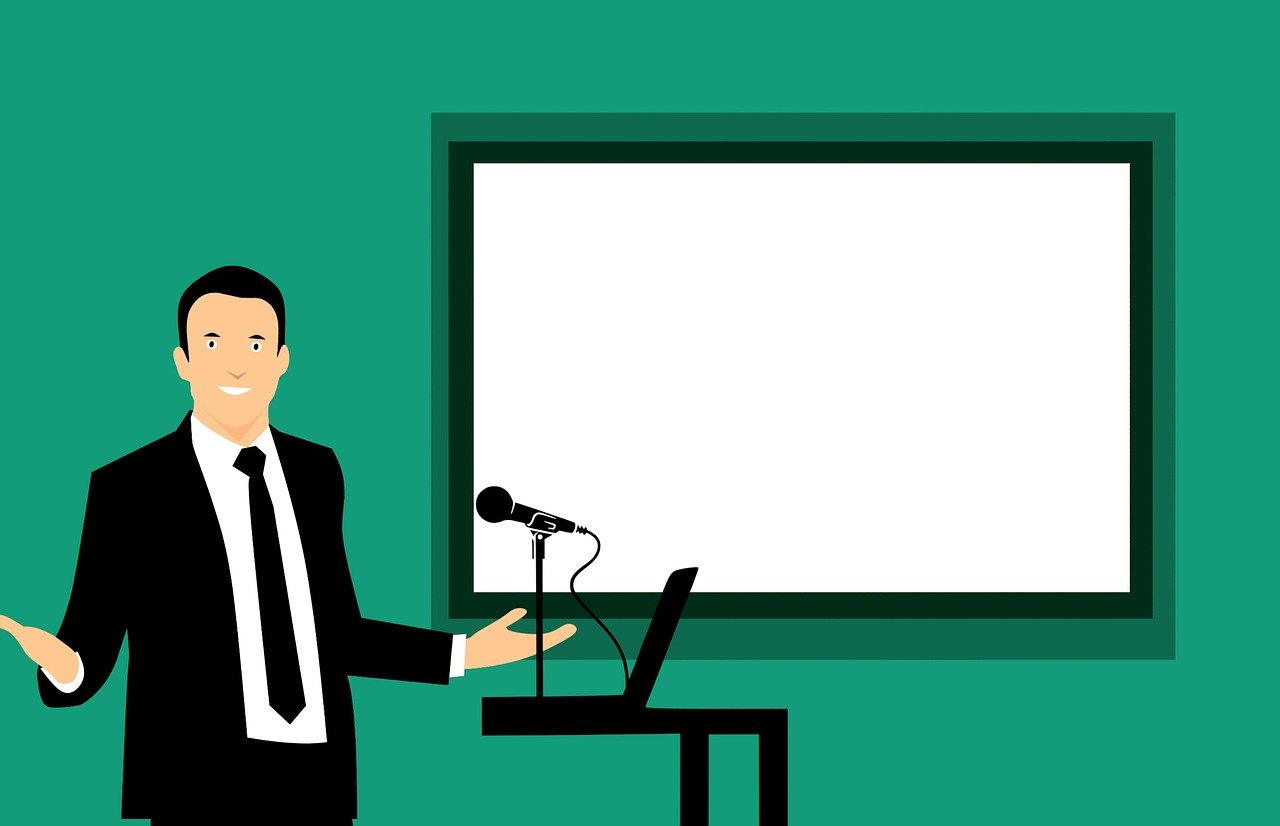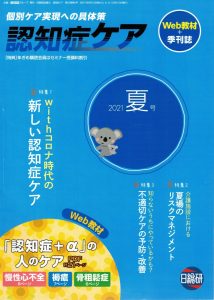「帰宅欲求」や「介護拒否」など認知症の人のBPSD(行動・心理症状)に困難を感じていませんか。
このように感じている方は、アセスメントの視点を変えてみることも一つの方法だと思います。
私も、認知症ケアの現場で仕事をしていたときは、認知症の人の言動に戸惑ったり、困難さを感じていた一人です。
しかし、認知症の人の帰宅欲求や介護拒否などといった目に見える言動ばかりではなく、その人の言動の原因を考え、立場を想像することで、認知症の人へのかかわり方が変化しました。
その結果、認知症の人の「帰宅欲求」や「介護拒否」といった行動も軽減しました。
残念ながら、認知症の人の言動に対して「この対応をすれば落ち着きます。」といった決まった方法はありません。
しかし、少し時間はかかるかもしれませんが、アセスメントの視点を変え、その人のニーズに基づいたケアを実践していくことで、帰宅欲求や暴言、暴力、ウロウロと歩き回るといった行動は軽減します。
この記事が、認知症ケアに悩んでいる現場の介護職員のお役に立てたら幸いです。
目次
認知症ケアにおけるアセスメント
介護福祉によるアセスメントは、自立支援のサービスを提供するために必須の、情報収集と分析・評価・働きかけのことです。
では、認知症の人のアセスメントではどのような情報を収集すればよいのでしょうか。
アセスメントシートやフェイスシートで見かけるのは、
〇認知症の有無
〇認知症の原因疾患(アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症など)は何か
〇「帰宅願望」「徘徊」などといった認知症の人のBPSD(行動・心理症状)の有無
などです。
確かに、これらの情報を収集することは必要なことです。
しかし、認知症ケアの専門職として、個別性を持ったケアを提供するためには、このような情報収集だけでは足りません。
認知症の人は、脳の障害により記憶障害や判断力の低下といった中核症状が現れます。
そして、中核症状によって、自らのことを正確に相手に伝えるというコミュニケーション能力に障害が起きることが特徴として挙げられます。
このように考えると、認知症ケアの専門職としては、認知症の人の言動(帰宅願望やウロウロと歩き回る、暴力行為など)を、認知症の人が発しているメッセージといて捉えることが必要になります。
「個別性のある認知症ケア」
つまり、個々の認知症の人のニーズ(生活全般の解決すべき課題)を満たすためには、認知症の人の言動の原因となっていることを情報収集し、そこに対してアプローチすることが必要です。
そのために、認知症の人の情報収集も「何が原因になっているか」といった視点で行う必要があります。
そこで、必要な情報は、先ほどお伝えした認知症の人のBPSD(行動・心理症状)だけでなく、ご本人の生活している環境や生活歴、性格など全人的に収集することになります。
アセスメントする内容
では、全人的に情報収集する必要があるとしても、具体的にどのような情報を収集すればよいのでしょうか。
ここでは、ひもときシート(監修:認知症介護研究研修・研究センター)の項目に沿ってお伝えしたいと思います。
ひもときシートは、アセスメントのためのツールではありませんが、認知症の人の情報を整理するためにはとても分かりやすいので参考にさせていただきます。
①認知機能障害・薬の副作用・疾患による影響
認知機能の低下により、相手の言っていること分からなかったり、自分の伝えたいことが伝えられずイライラしているのではないか。
見当識障害(時間や場所、人が認識できない障害)により、不安があるのではないか。
薬の副作用や薬の管理ができているか。 など
②体調不良や痛みによる影響
便秘は影響していないか。
疲れていないか。 など
③性格や精神的苦痛による影響
元々の性格が心配性で、家のことが心配なのではないか。
自分のペースで行動したい人なので、周囲から何か行動を強制されることを嫌がっているのではないか。 など
④音や光など感覚刺激による影響
今いる場所(グループホームやデイサービスなど)は、テレビや職員の音が大きくて不快に感じてるのではないか。
聴覚に障害があり、周囲の人が自分の悪口を言っていると思っているのではないか。 など
⑤人からのかかわりによる影響
家族とかかわりが少なくなり、不安を感じているのではないか。
職員に何度も声掛けをされるので、イライラしているのではないか。 など
⑥物理的環境による影響
現在の場所に置いてある物が、自宅の生活様式と違うのではないか。
自分の部屋やトイレの場所が分からずに困っているのではないか。 など
⑦アクティビティ(活動)による影響
散歩や買い物など外出がしたいのではないか。
次に何をしたら良いかわからないため、不安を感じているのではないか。 など
⑧生活歴によって培われたものによる影響
これまで長年やってきた仕事や家事、趣味などが行動に影響してないか。 など
まとめ
このように、アセスメントの視点を変えることにより、
帰宅欲求のある人→ここがどこか分からないかわいそうな人
介護拒否がある人→難しい人・わがままな人
といった思考から、「なぜ家に帰りたいというのか」「なぜ介護を拒否するのか」と少しずつ思考が変化してくるのではないでしょうか。
もちろん、原因がすべてわかるといったことはないと思います。
しかし、ご本人の言動の原因を考え、原因に対してアプローチすることが個別性がある認知症ケアにつながると思います。