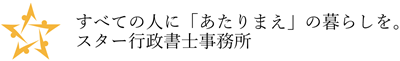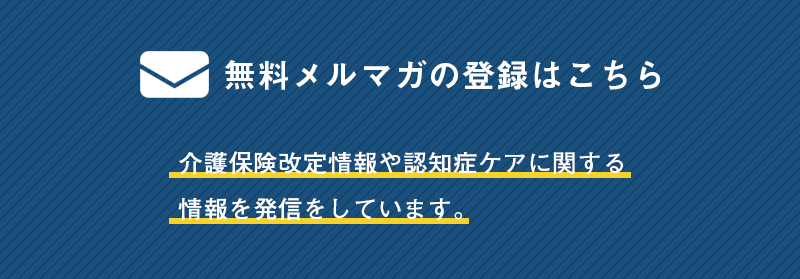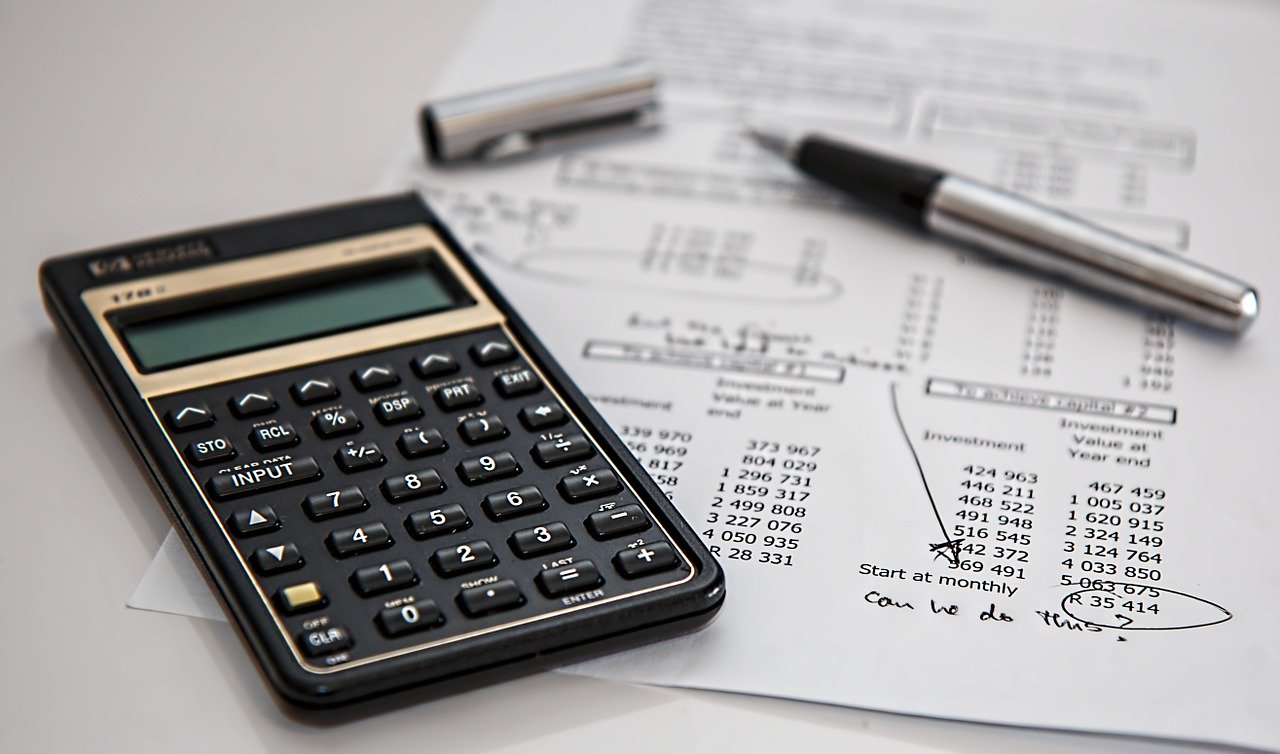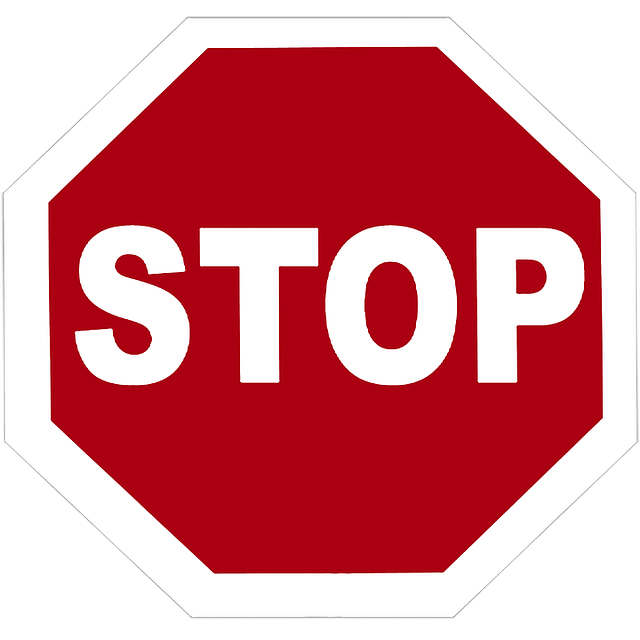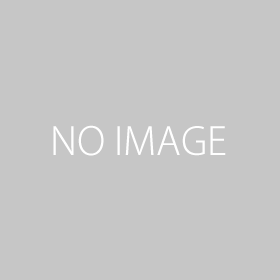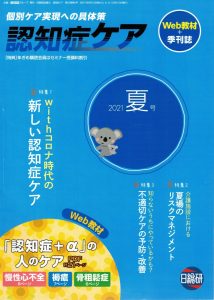皆さんの事業所では、歩行が不安定にもかかわらず、車いすから一人で立ち上がる認知症の人をどのような方法で介護しているでしょうか。
2000年に介護保険制度が開始になってから、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束は禁止になり、現在は、車いすから立ち上がれないようにベルトを使用することはないと思います。
しかし、以前は認知症の人を抑制したり、認知症の人のBPSD(行動・心理症状)に上手に対応することが認知症ケアだと考えられてきました。
例えば次のような介護方法です。
| 認知症の人の行動 | 介護方法の例 |
| 車いすから立ち上がる | 車いすから立ち上がれないようにベルトを使用する |
| ベッドから歩き出す | 4点柵や抑制帯を使用する |
| 「家に帰ります」と言ってウロウロする | 「もうバスが終わってしまったので、明日帰りましょう。」と声をかける
諦めるまで待つ |
| 共同スペース(リビングなど)に置いてある物を持っていく | 共同スペース(リビングなど)に物を置かない
取り上げる |
| 他のご利用者の食事に手が出る | 1人の食席にする |
このように、認知症の人の状態(様子)にどのように対処していくかが認知症ケアの中心とされてきました。
では、そもそも認知症の人の状態(様子)は、なぜ起こるのでしょうか。
目次
認知症の状態に与える影響
パーソン・センタード・ケアの考え方を示した英国ブラッドフォード大学のトム=キットウッド教授は、認知症の状態は次の5つの要素が影響し合っていると考えました。
〇脳神経障害
〇性格傾向:気質、能力、対処スタイル
〇生活歴
〇健康状態・感覚機能:視力、聴力等
〇その人を取り囲む社会心理:人間関係のパターン
順にみていきましょう。
脳神経障害
認知症の原因疾患の主なものとして
①アルツハイマー型認知症
②脳血管認知症
③レビー小体型認知症
④前頭側頭型認知症
があります。
これらはすべて何らかの原因で脳の神経細胞がダメージを受けています。
そして、脳がダメージを受けたことによって中核症状が現れます。
アルツハイマー型認知症の症状の記憶障害や見当識障害、レビー小体型認知症の人の幻視は代表的な中核症状です。
性格的傾向:気質、能力、対処スタイル
私は以前、地域住民を対象に認知症の勉強会を行ったことがあります。
勉強会終了後、参加した人たちと一緒にお茶を飲んでいると、Aさんは「私は、絶対認知症になりたくないわ。認知症のなったら部屋の中も整理できなくなるし、着るものもわからなくなるなんて嫌だわ。だから、一生懸命認知症の予防します。」と言いました。
同じ場所にいたBさんは、「認知症になったらなったで仕方がない、誰かに世話をしてもらいながら、自分のできることをしながら楽しく過ごしますよ。」と言いました。
どちらの性格が良いとか悪いではなく、人によって性格傾向は異なります。
この人達が認知症になった時に、Aさんは日々不安や葛藤の中で生活するかもしれませんが、Bさんは、あまり気にせずにおおらかに日々の生活を送るのではないでしょうか。
このように元々の性格傾向は認知症になっても影響すると考えられます。
生活歴
自分たちが生まれ育った環境や、家族関係、職業などは知らないうちに自分たちに影響を及ぼしていることがあります。
グループホームに入居していたIさんは、散歩中の道路や居室横のベランダで排尿していました。
介護職員も排尿リズムを把握するように努め、時間を合わせてトイレに行くように声掛けをしていましたが、トイレ以外の場所での排尿はなくなりませんでした。
ご家族に尋ねたところ、Iさんは何十年も農業をやっており、昔からトイレで用を足す習慣がなかった、ということでした。
きっと、認知症になる前から畑のどこかで用を足していたのでしょう。
また、特別養護老人ホームのご利用者Yさんは、毎晩20~21時に、他の居室の入り口を除いてから自分が就寝するという習慣がありました。
その方は、長い間刑務官として働いており、夜間勤務のときは刑務所内の見廻りをしていたそうです。
特別養護老人ホームを自分の家ではなく職場だと思われていたのは残念ですが、夜間、他のご利用者の居室を覗くというのは、Yさんなりの理由があったのです。
また、Nさん(女性)は、夜間、自分の居室のドアの取っ手と壁の手すりをタオルできつく結び、夜間、誰も居室に入れないようにしていました。
ご家族のお話では、Nさんはご主人がお亡くなりになってから、長年一人で暮らしていたため、自宅の戸締りはとても慎重だったとのことでした。
このように、このような生活歴は、認知症になってもその人の行動に影響を与えています。
健康状態、感覚機能(視力、聴力等)
身体状態がその人の認知症の状態に影響を与えていることを意味しています。
例えば、便秘をしていて腹部に不快感がある、歯が痛い、など。
認知症の人は、認知機能の低下により、自分のことを正確に相手に伝えることが困難になります。
その結果、その人なりの表現(大声を出したり、テーブルを叩いたり)をすることあります。
また、視力低下によって周囲に誰もいないと思い「誰かいませんか!お願いします!」と大声で不安を訴える人がいました。
その場合、介護職員が「ここにいますよ。」と肩をポンと叩けば安心することも多くありました。
これは、感覚機能の低下によって認知症の症状が出現するという場面です。
その人をめぐる社会心理学的状況
認知症の人が置かれている環境(主に人間関係)のことです。
例えは、認知症の人の周囲にいる人たちが、認知症の人に対して無視をする、人扱いしない、差別するといった環境にあるのと、温かく思いやりのある支援がされる環境では、認知症の症状は変わってくると考えます。
以上、トム=キットウッド教授が考える認知症の症状を起こす原因についてみてきました。
認知症の人をとらえる
最初に挙げた脳神経障害は、現在治療する方法はありません。
だからといって、脳神経障害の理解をしなくて良いということではなく、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症といった原因疾患によって、中核症状が異なるため、認知症ケア専門職として原因疾患を理解することはとても大切なことです。
しかし、認知症の人の様子は、すべての脳の神経障害が原因しているということではなく、その人の性格傾向や育った環境、生活歴、健康状態、人や社会との付き合い方などの影響が大きいといえます。
このような意味で「認知症の人」ではなく、「認知症の人」という視点が認知症ケアには必要だと思います。

認知症ケアの現場では、認知症の人の行動に対して「ニンチ入ってるから。」「ニンチだから仕方がない。」という言葉を聞くことがあります。
確かに、脳の機能障害によって様々な行動が出ることもあると思います。
しかし、その「人」を知ることにより、その人の行動の意味が理解できることもあるかもしれません。
パーソン・センタード・ケアでは、認知症の人の「病気」を中心にとらえるのではなく、その「人」を中心にし、認知症の人が何に困っているのか、何を求めているのかを考え、その人にどのようにかかわっていくかを中心に考えることが大切であるといえます。