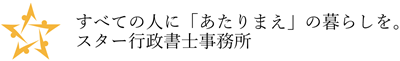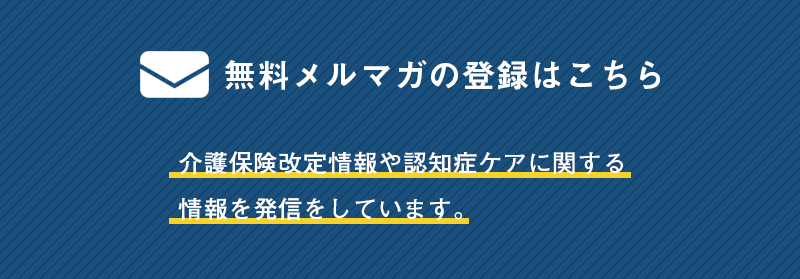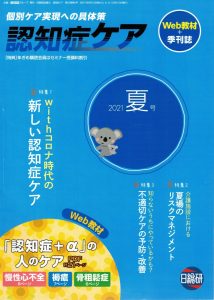目次
リハビリ型デイサービスとは
リハビリ型デイサービスと介護保険制度
リハビリ型デイサービスは、介護保険制度に基づいて提供される介護サービスです。
介護保険制度の中にはリハビリ型デイサービスという名称のサービスはなく、制度上はデイサービスに分類されます。
通常のデイサービスは、1回7~8時間、事業所内で食事や入浴、レクリエーションなどを提供しますが、機能訓練型デイサービスは3時間程度、日常生活の中での身体機能の維持・改善を目的にした機能訓練を提供し、食事や入浴は行ないません。
一日の主な流れは、
①迎え
②到着後、健康チェック(血圧・体温・脈拍の測定)
③準備体操
④マシントレーニング
⑤休憩
⑥個別機能訓練
⑦健康チェック(血圧・体温・脈拍の測定)
⑧送り
といった内容です。
リハビリ型デイサービスと通所リハビリテーションの違い
リハビリ型デイサービスと似た介護サービスに、通所リハビリテーション(デイケア)があります。通所リハビリテーションは、ご利用者が老人保健施設や病院・診療所などに通って、医師の指示に基づき、リハビリテーション計画に沿ったリハビリテーションを行います。
主な違いは以下の通りです。
| リハビリ型デイサービス | 通所リハビリテーション(デイケア) | |
| 内容 | 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。 利用者が通所介護の施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 |
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。 |
| 実施主体 | 株式会社、合同会社、社会福祉法人など | 主に医療法人 |
| 主な目的 | 高齢化によって衰えがちな日常生活の機能を維持・改善 | 病気療養後の在宅復帰や心身の機能の維持・回復 |
| 医師の指示 | 不要 | 必要 |
| 人員基準 | 【生活相談員】
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上 【看護職員(看護師・准看護師)】 単位ごとに専従で1以上 【介護職員】 ① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式) 【機能訓練指導員 】 1以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) |
【医師】
専任の常勤医師1以上(病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可) 【従事者 (理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員)】 単位ごとに利用者10人に1以上 【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士】 上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上 |
| 設備基準 | 【食堂・機能訓練室】
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上 【相談室】 相談の内容が漏えいしないよう配慮されている |
【リハビリテーションを行う専用の部屋】
指定通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋(3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上)設備 |
リハビリ型デイサービス開業までの流れ
次にリハビリ型デイサービスの開業までの流れをみてみましょう。
リハビリ型デイサービスの許認可には1~2カ月くらいが目安になりますが、地域によって若干異なりますので、事業を行おうとする都道府県や市町村に確認することが必要です。
リハビリ型デイサービスを開業するまでに必要な流れは次の通りです。
①開業地域の選定と決定
高齢者の人口や競合他社の状況、地域ニーズの把握が必要になります。
②物件選び
物件の選定には店舗改修、民家活用、新築などの方法があります。
そして、事業を開始するためには省令で定められた定員1人あたり3㎡以上の設備基準を満たす必要になります。
③資金の調達
自己資金以外で、日本政策公庫など金融機関からの融資や、補助・助成金の活用などがあります。
④人材の確保
ご利用者の定員数によって配置すべき職員数や必要な資格が決められていますので、必要な数の職員を確保しておく必要があります。
最近は介護職員を募集しても集まりにくい状況が続いています。人材を確保するためには、労働基準法を遵守することは当然ですが、それ以外にも働きやすい職場環境を作る、事業所の特色や管理者の「想い」をアピールすることが大切です。
⑤必要な申請をする
リハビリ型デイサービスを立ち上げるためには、法人格(株式会社、合同会社、NPO、社会福祉法人など)を取得しなければなりません。
また、都道府県や市町村から介護保険事業者としての指定を受ける必要があります。
この指定を受けるためには、前に記載した人員基準と設備基準を満たしていなければなりません。
⑥物品や事務機器、特殊車両の準備
機能訓練のために必要な機材や事務用品を準備します。
また、介護報酬の請求は、国民健康保険団体連合会(国保連)へインターネットを利用して行われますので、インターネット環境が必要になります。送迎の時に使用する車も準備する必要があります。
⑦地域のケアマネージャーや地域包括支援センターへ開業の周知
居宅介護支援事業所のケアマネージャーや包括支援センターへ開業のお知らせをします。
以上が開業までの流れになります。
ご利用者がリハビリ型デイサービスを利用するまでの流れ
介護保険制度の下で運営をしているデイサービスを利用するときは、以下の手続きが必要になります。
①要介護認定の申請
②認定調査・主治医意見書
③審査判定
④認定
⑤介護計画(以下:ケアプラン)の作成
⑥利用開始
具体的に①~⑥までを見ていきましょう。
①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請の窓口は住んでいる市区町村の窓口になります。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です
②認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
④認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
⑤介護計画(以下:「ケアプラン」といいます)の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、ケアプランの作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防ケアプランは地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上のケアプランは介護支援専門員(以下:「ケアマネージャー」といいます)のいる、指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けたケアマネージャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、ケアプランを作成します。
⑥リハビリ型デイサービスの開始
ケアプランに基づき、リハビリ型デイサービスの利用が開始になります。
介護報酬とリハビリ型デイサービス事業所の収入
介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に対して支払われる報酬のことをいいます。
介護報酬は基本報酬と加算の二層構造になっています。
介護報酬は全国一律の基準になっており、3年に1度改定されます。
基本報酬
基本報酬は、基本的なサービスの提供かかる報酬です。
ケアプランに定められたサービスを、定められた時間で提供することで請求できる介護サービスの料金です。
基本単位数は次のようになっています。
| 小規模型(利用定員18人以下) | 通常規模型(利用定員19以上) | |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1:407単位
要介護2:466単位 要介護3:527単位 要介護4:586単位 要介護5:647単位 |
要介護1:362単位
要介護2:415単位 要介護3:470単位 要介護4:522単位 要介護5:576単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護1:426単位
要介護2:488単位 要介護3:552単位 要介護4:614単位 要介護5:678単位 |
要介護1:380単位
要介護2:436単位 要介護3:493単位 要介護4:548単位 要介護5:605単位 |
加算
介護報酬は基本報酬だけでなく、基本報酬に各種加算を加えて算定する仕組みになっています。
加算を算定するためには規定された算定要件を満たす必要があります。
機能訓練型デイサービスの加算として個別機能訓練加算があります。
単位数と算定要件は以下の通りです。
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算(Ⅱ) | |
| 単位数 | 1日につき46単位 | 1日につき56単位 |
| 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師 )の配置 | 常勤・専従1名以上配置 (時間帯を通じて配置) |
専従1名以上配置 (配置時間の定めはない) |
| 個別機能訓練計画 | (利用者ごとに心身の状況に応じた上で) 多職種共同で作成 |
(利用者ごとに心身の状況に応じた上で) 多職種共同で作成 |
| 機能訓練項目 | 利用者の自立支援と日常生活の充実に資するよう複数種類の機能訓練項目 | 利用者の生活機能向上を目的とする 機能訓練項目(1人でお風呂に入る等といった生活機能の維持・向上に関する目標設定が必要) |
| 訓練の対象者 | 人数制限なし | 5人程度以下の小集団又は個別 |
| 訓練の実施者 | 制限なし (必ずしも機能訓練指導員が直接実施する必要はなく、機能訓練指導員の管理の下に別の従事者が実施した場合でも算定可) |
機能訓練指導員が直接実施 |
| 実施回数 | 実施回数の定めはない | 概ね週1回以上実施 |
※機能訓練指導員が2名配置されていれば、同一日に同一の利用者に対して両加算を算定することも可能。
※機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていることが必要((Ⅰ)及び(Ⅱ)共通))
サービスを提供した後、事業所に入金されるまでの流れは次の通りです。
1月 サービス提供
2月 10日までに国保連に介護報酬の9割(利用者自己負担1割の場合)を請求、利用者に自己負担分(原則1割)を請求・入金
3月 25日国保連からの入金
ご利用者に介護サービスを提供した場合、ご利用者は1割(原則)を負担し、それ以外の9割は市町村から事業所に支払われます。
【例:要介護度1の人が定員10人のリハビリ型デイサービスを3~4時間利用、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定した場合】
407単位+46単位×10(地域によって異なります)=4,530円
1回につき453円(1割)が利用者負担額となります。
機能訓練型デイサービスを運営する上で重要なこと
ここまでは、事業を始めるために必要な制度や開業までの流れについてみてきました。
最後にリハビリ型デイサービスを開業後、安定した運営を継続するために特に重要な点をお伝えします。
法人理念の共有
理念とは「根底にある基本的な考え方」(広辞苑)です。
「理念」と聞くと、介護の仕事をする上であまり必要ないと思われるかもしれませんが、職員が法人の理念を理解し、共有することは非常に重要なことです。
なぜかというと、事業所には、経験年数や知識、保有資格、年齢など色々な職員が働いています。
事業所を運営していく中で、課題に直面した時に職員が自分の考えていることを述べ、議論することはとても大切なことです。
しかし、それではいつまでも課題が解決しない場合もあります。
そういった場合、法人の理念を根拠にしてチームを一つにまとめたり、法人の方向性を決めることが必要になります。
人材育成
事業所を運営するにあたり、職員を対象に認知症ケアやプライバシーに関する研修を行わなければなりません。
介護サービスは基本的には「人」が「人」にサービスを提供するものです。職員の質の向上はより良いサービスの提供のために欠かせません。
事業開始後には事業内研修だけでなく、外部研修にも積極的に参加する必要があると考えます。
職員の採用
現在介護人材は、募集をしても集まりにくい状況です。
そこで、求人をどのような方法で集めるかを考える必要があります。
フリーペーパーや新聞の折り込み、インターネットの求人サイト等が考えられますが、募集する人材の年齢などを考慮して、募集することが必要になってきます。
事業所のホームページを作り、色々な情報を発信しながら求人を集めることは効果的だと思います。
介護報酬の改定に対応する
介護報酬は3年に一度、改定があります。
この改定によって、介護報酬額が変わったり、新しい加算が算定できるようになったりします。
その結果、デイサービスの経営に大きな影響を与えます。
改定前には、厚生労働省から情報が出ていきますので、アンテナを立て、情報収集が必要になります。
これまでの介護報酬改定の主なポイントです。
| 年度 | 改定のポイント |
| 2003年 | ・自立支援の視点に立ったケアマネジメントの確立
・自立支援を思考する在宅サービスの強化 ・施設サービスの質の向上と適正化 |
| 2005年 | ・居住費・食費に関する介護報酬の見直し
・居住費・食費に関する運営基準の等の見直し |
| 2006年 | ・中重度者への支援強化
・介護予防、リハビリテーションの推進 ・地域包括ケア、認知症ケアの確立 ・サービスの質の向上 ・医療と介護の機能分担・連携の明確化 |
| 2008年 | ・療養病床の一層の転換促進を図るための介護老人保健施設等の基準の見直し |
| 2009年 | ・介護従事者の人材確保・処遇改善
・地域包括ケア、認知症ケアの充実 ・効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証 |
| 2012年 | ・地域区分の変更による報酬単価の見直し
・介護職員処遇改善交付金の加算としての存続 ・基本単位の見直し ・加算の見直し ・利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する減算 |
| 2015年 | ・地域包括ケアシステムに向けた在宅中重度者や認知症高齢者への対応の強化
・介護人材確保への対策の推進 ・サービス評価・適正化と効率的なサービス体制の構築 |
| 2018年 | ・地域包括ケアシステムの推進
・自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現 ・多様な人材の確保と生産性の向上 ・介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保 |
まとめ
以上、リハビリ型デイサービスを開業する前に知っておくべき基礎知識のお伝えしました。
介護保険制度が始まった時のデイサービスの数は7,133でしたが、2017年には43,442に増加しています。今後も高齢者が増加することから介護事業の将来性を感じて参入する方も多いと思います。
しかし、これまで見てきたように介護事業は、介護報酬の改定によって大きな影響があります。また、人員の確保といった問題もあります。
安易に介護事業を開業して「儲からないからやめる」というわけにいきません。
ここまで読んでいただいたのは、開業についての思いが強いからだと思います。
自分自身の理想の事業所像を描いて、しっかりと準備をして開業に向けて頑張ってください。
最後までお読みいただきありがとうございました。